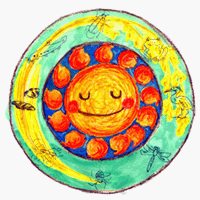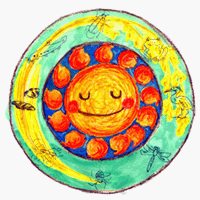
おひさま米のページにお越しくださりありがとうございます。
2022年5月よりクレジット決済を導入いたしましたことより、カート内で価格が即時確定できる送料にする必要のため、これまで1kg単位でお受けしていたご注文単位を、送料との対応との関係でいくつかの数量に絞って表示しています。なお、ご自由な数量、あるいは組み合わせ同梱でのご購入をご希望の場合は、下記の申し込みフォーム、あるいは普段やりとりしておりますメールよりご注文をお願いしたく、宜しくお願いいたします(その際はクレジット決済にはなりません)。今後改良を加えてまいりますので、引き続き宜しくお願い申し上げます。
▼お問い合わせフォームに移動する
お米の計量について
当園では玄米でのご希望の方が多く、玄米基準での計量にて出荷とさせていただいています。精米でのお届けの方は米ぬか分が減ることになりますが、米ぬかを添付しております(オプションで選択してください)。農薬は使用していないので安心して漬け物等にご使用ください。なお冬以外には虫が発生しやすいので、米ぬかの保管にはどうぞご注意ください(冷蔵は必須です)。

小規模の家族労働で作業を進めています。規模は小さいですが、稲作という農耕文化の意味を確かめつつ、野良の営みに向き合っていきたいと思っています。

【使用資材・肥料】
米ぬかのみ(亀の尾等完全に無肥料の栽培もあります)
米ぬか中心の米つくりです。
お米の食味を上げるのは米ぬかが適しているといわれます。乳酸菌の補給にもなります。地域内で精米された米の米ぬかを採取して、春の元肥として田に散布します。また全部の田ではないですが、田植え後にイネの根が活着してから、畦畔より、そして田の中を歩いて風向きを考慮しながら手で撒き散らします。そのうちに糸ミミズが発生し、土もトロトロになって米ぬか層を形成します。

除草はチェーン・エンジン除草機・下駄除草、そして手取りを組み合わせています。
除草は一番の作業労苦になります。器具を使って頑張りますが、最後は手取りです。。除草機は 雑草も初期の小さいうちのもので、大きくなりますと条間は下駄で沈め、株間は手で取るしかありません。取るといっても、土の中に埋め込むのですが。これらも7月の第1週までです。その後は中干しして土を固めるので、草取りはもうしません。なるべく深水にしてヒエを始め草を抑えるべく努力はするのですが、畦畔の低いところがあったり、田面も高低差があったり、難しいものです。

自然乾燥の米作りです。
1束ずつイネを上げていく作業。 刈っていく機械作業の2倍以上かかります。その日刈り取ったイネはその日のうちに掛けなくてはいけないので、計画的に作業を進めます。1年の農作業のハイライトです。でも刈りたてのイネのにおいは良いですよね。子どもがたまたま軽トラの 荷台に乗っている写真ですが、稲の束は運搬車(キャリア)で田の中からハサ場まで運びます。栗の木の柱に結ぶ横の棒は、当地ではスギの間伐材を使っており(竹を使っている地域もあるようですが)、「ホケ」と呼んでいます。稲刈り時期になると作業場の2階からホケを下ろしてハサ場まで運んで組み立て、稲扱きが終わるとほぐしてまた作業場まで引きずって運び、2階へ上げる。結構大変な作業です。雪の少ない地方だと、ハサ場のそばにホケをしまっておく簡単なトタンの収納場を作っていますが、豪雪地ではなかなか簡単なものではすまされません。
掛けて約1週間で水分17%まで下がり、新米時期の短期貯蔵消費分としては実に瑞々しく美味しいお米になります。約3週間で16%まで下がり、標準の出荷米とし、さらに最初からハウス内で雨避け乾燥させたものは15%台まで乾燥し、翌夏の最後の出荷分にしています。
あすこの田はねえ (稲作挿話より)
あすこの田はねえ
あの種類では窒素があんまり多過ぎるから
もうきっぱりと灌水(みず)を切ってねえ
三番除草はしないんだ
・・・・・・一しんに畔を走ってきて
青田のなかに汗拭くその子・・・・・・
燐酸がまだ残ってゐない?
みんな使った?
それではもしもこの天候が
これから五日続いたら
あの枝垂れ葉をねえ
斯ういふ風な枝垂れ葉をねえ
むしってとってしまうんだ
・・・・・・せわしくうなづき汗拭くその子
冬講習に来たときは
一年はたらいたあととは云へ
まだかがやかな苹果(りんご)のわらひを
もってゐた
いまはもう日と汗に焼け
幾夜の不眠にやつれてゐる・・・・・・
それからいいかい
今月末にあの稲が
君の胸より延びたらねえ
ちゃうどシャツの上のボタンを定規にしてねえ
葉尖(はさき)を刈ってしまふんだ
・・・・・・汗だけでない
泪も拭いてゐるんだな・・・・・・
君が自分でかんがへた
あの田もすっかり見てきたよ
陸羽一三二号のはうね
あれはずゐぶん上手に行った
肥えも少しもむらがないし
いかにも強く育ってゐる
硫安だって君が播いたろう
みんながいろいろ云ふだらうが
あっちは少しも心配ない
反当三石二斗なら
もうきまったと云っていい
しっかりやるんだよ
これからの本当の勉強はねえ
テニスをしながら商売の先生から
義理で教はることでないんだ
きみのやうにさ
吹雪やわづかの仕事のひまで
泣きながら
からだに刻んで行く勉強が
まもなくぐんぐん強い芽を噴いて
どこまでのびるかわからない
それがこれからのあたらしい学問のはじまりなんだ
ではさやうなら
・・・・・・雲からも風からも
透明な力が
そのこどもに
うつれ・・・・・・
当園では2012年まで3度、「陸羽132号」を作付けしました。当地は 賢治先生の時代の花巻よりもやはり寒くて、適地ではありませんでしたので、2013年からは栽培を終了しました。美しい、印象的な文章ですね。