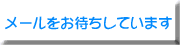りんどう
 奥羽の山里は花の産地。日内温度差が激しいことで、花が鮮やかな色となり、高い評価を受けてい ます。紅葉と同じ理屈でしょうか。仙台から移植して植えてみたバラの花も、ここではよりいっそう鮮やかな色づきのようで、あらためて気象条件の差というも のを感じさせます。
奥羽の山里は花の産地。日内温度差が激しいことで、花が鮮やかな色となり、高い評価を受けてい ます。紅葉と同じ理屈でしょうか。仙台から移植して植えてみたバラの花も、ここではよりいっそう鮮やかな色づきのようで、あらためて気象条件の差というも のを感じさせます。
わが家のりんどうの品種は、早い方から、「いわて夢あおい」「さわ風1~3」「雪の舞」「蒼い風 早生」「サマーエレガンス」「マーメイド」「蒼い風」「藍の風」「雪ほたる」「アルビレオ」の12品種(2012年採花品種)。ほとんどがここ西和賀地域 オリジナルの品種を植えていますよ。約2週間で1品種のりんどうが咲き移っていき、7月下旬~10月いっぱいはいつでも何かが咲いている形です。

 上の写真は1996年、移住した年、初めてりんどう苗を定植した記念すべきもの。近 所のおばさんたちに手伝ってもらい8,000本を、腰を痛くしながら。そして年月は経ち当初の1反分から7反分にまで拡張した。8~10月はひたすら出荷 作業が夜遅くまで続きます。
上の写真は1996年、移住した年、初めてりんどう苗を定植した記念すべきもの。近 所のおばさんたちに手伝ってもらい8,000本を、腰を痛くしながら。そして年月は経ち当初の1反分から7反分にまで拡張した。8~10月はひたすら出荷 作業が夜遅くまで続きます。
現在は通路を広く空ける傾向になり、10アール株本数は7,000本以下になっているでしょうか。特に周囲を 広くとって畝作りをすることが、土壌病害(センチュウの侵入や原因不明の株を根絶させる病害)から守ってくれるのです。排水のことも考えて、畦畔内側に 沿ったほ場外周には溝を掘ることも盛んに行われています。
り ん ど う は こ う 採 る






りんどうの1年
 雪解け後、アスパラのようににょきにょき生えてくるのが4月下旬。肥料をやり、雪で曲がったり折れたりした支柱を直してやって、冬の間地面まで下げておいたネットを作業の関係で いったん上げる。そして5月の連休後あたりから株仕立て(通称「芽かき」という)作業に着手です。約 1か月もかかっててたくさん立ってきたりんどうの芽を8本くらいに掻いてやる作業が続きます。芽かきが終わった畝からりんどうの高さに合わせてネットを下 げて、まずは初期作業が一段落。休む間もなく、新しいりんどう苗を定植するのもこの晩春の時期。また 定植翌年の2年目の畑には支柱を立てネットを掛ける作業が加わります。りんどうがネットを要求する時 期までには終わらせないと。。
雪解け後、アスパラのようににょきにょき生えてくるのが4月下旬。肥料をやり、雪で曲がったり折れたりした支柱を直してやって、冬の間地面まで下げておいたネットを作業の関係で いったん上げる。そして5月の連休後あたりから株仕立て(通称「芽かき」という)作業に着手です。約 1か月もかかっててたくさん立ってきたりんどうの芽を8本くらいに掻いてやる作業が続きます。芽かきが終わった畝からりんどうの高さに合わせてネットを下 げて、まずは初期作業が一段落。休む間もなく、新しいりんどう苗を定植するのもこの晩春の時期。また 定植翌年の2年目の畑には支柱を立てネットを掛ける作業が加わります。りんどうがネットを要求する時 期までには終わらせないと。。
やがてりんどうはすくすく伸び、生育に合わせてネットを上 げてやります(曲がるとB品になり値段が安くなるわけです)。そしてはびこってくる雑草取りと病害虫の防除の時期に。強風や大雨が降った後は念入りにネット作業をしないと曲がってしまいます。
そうこうしているうちに盛夏となり、早生品種から収穫期に突入。この期間はひたすら収穫・選別の繰り返す日々、、。最大の山場は需要期であるお盆と秋彼岸の1週間前です。
稲刈り後も採花は続き、や がて3か月に及ぶ収穫期が終わります。秋も深まり霜が降ってくるようになるとりんどうも枯れてくるので、早生の品種から、草刈り機で枯れてきたりんどうを刈り、かき集めて運び出す。これがけっこう大変な作業。寒くなりみぞれも降ってきたりして 辛いです。そして片づいたら最後に畝の間に堆肥を施して、ネットを地際まで下げて、1年が終わりま す。 早生品種の場合、春一番に効かせるためここで翌年のための施肥を行う傾向になっています。
秋は日が短く、雪に覆われる日も早い。4月下旬から11月月中旬まで、気ぜわしく作業が続くのです。冬は雪の 下ですが、かえって温かい雪の布団に覆われて株は守られているので、雪のない寒風にさらされる地方よりもりんどうにとっては結構なんですね。残雪で春の初 期生育が遅れるのは痛手なんですけど。
りんどうの選別作業
 収穫したりんどうは作業場に移送して、選別作業が始まります。1本1本を限られた時間で瞬時に選別し、大量の 本数を扱わなくては仕事にならず、経験と勘が求められますね。収穫したりんどうは畑でフラワーカーで採った時の緑の網のまますぐに水に漬け、ある程度水が揚がったら選別に着手し、規格ごとに10本ずつ結束した束を今度はまた別の水槽に 立てて、水揚げを進めます。そして翌朝、りんどうを箱詰めし(1箱約150本入り)、町道沿いの車庫 に置いておくと、JAのトラックが持って行ってくれます。関東・関西・九州等がメイン市場になるでしょうか。一応全国に発送されています。
収穫したりんどうは作業場に移送して、選別作業が始まります。1本1本を限られた時間で瞬時に選別し、大量の 本数を扱わなくては仕事にならず、経験と勘が求められますね。収穫したりんどうは畑でフラワーカーで採った時の緑の網のまますぐに水に漬け、ある程度水が揚がったら選別に着手し、規格ごとに10本ずつ結束した束を今度はまた別の水槽に 立てて、水揚げを進めます。そして翌朝、りんどうを箱詰めし(1箱約150本入り)、町道沿いの車庫 に置いておくと、JAのトラックが持って行ってくれます。関東・関西・九州等がメイン市場になるでしょうか。一応全国に発送されています。
 りんどうは原則毎日出荷。したがって、雨の日も当然収穫します。その時に役立つのが乾燥機です。写真に写っていませんが、黄色のボックスの右側に灯油のジェッ トヒーターがあって、黄色の箱の右側に付いている大きな200Vの扇風機がヒーターの 熱を内側に強制的に引きずり込み、そして濡れたりんどうを灰色のバケツに立てて、黄色のボックスの上に置くと、バケツの底が金網になっていて、立てたりん どうに下から温風が送り込まれて乾燥してくれます(写真は使用時でなくバケツを重ねて置いているだけ)。温度や時間はコントロールできます。
りんどうは原則毎日出荷。したがって、雨の日も当然収穫します。その時に役立つのが乾燥機です。写真に写っていませんが、黄色のボックスの右側に灯油のジェッ トヒーターがあって、黄色の箱の右側に付いている大きな200Vの扇風機がヒーターの 熱を内側に強制的に引きずり込み、そして濡れたりんどうを灰色のバケツに立てて、黄色のボックスの上に置くと、バケツの底が金網になっていて、立てたりん どうに下から温風が送り込まれて乾燥してくれます(写真は使用時でなくバケツを重ねて置いているだけ)。温度や時間はコントロールできます。
 目と手で選別したりんどうは、フラワーバインダーで結束 します。左の写真の緑色の機械です。やっているように、手前から10本ずつ送り込んでいくと、まず根元をモーターで回る丸い刃で切断し、次いで根元の20cmくらいの部分をゴムブラシ2個を組み合わせた装置で下葉取りします。そして葉を取った部分を2か所結束し、向 こう側に投げ出してくれます。この装置は最近普及し導入が進んできた機械ですが、以前は鋏で切り、軍手をはめた手で葉取りをし、輪ゴムで結束していまし た。
目と手で選別したりんどうは、フラワーバインダーで結束 します。左の写真の緑色の機械です。やっているように、手前から10本ずつ送り込んでいくと、まず根元をモーターで回る丸い刃で切断し、次いで根元の20cmくらいの部分をゴムブラシ2個を組み合わせた装置で下葉取りします。そして葉を取った部分を2か所結束し、向 こう側に投げ出してくれます。この装置は最近普及し導入が進んできた機械ですが、以前は鋏で切り、軍手をはめた手で葉取りをし、輪ゴムで結束していまし た。
順番で追うと、収穫・選別・切断結束・(乾燥)・水揚げ・箱詰め、となります。
当園はりんどうは系統市場出荷になり、インターネットでの米や野菜等の直接販売とは部門が異なります。りんど うはある意味個性ある農業の姿とは言えない共選共販で、地域で同じ品質の物を出荷するものです。これが「産地」として地域全体の特産品として特徴を出して いく動きになるわけですね。
他の花々
 小さい花がつぶつぶに寄り集まったアスチルベの花姿。アスチルベは宿根草で、1営農用品種として少量購入した苗を時間をかけて大きい株とし、それを株分けして数を増やしたものを出荷していました。”りんどう農家”にとっては6月 中旬から7月中旬までの1か月は、比較的時間に余裕のある時期。現在ではメイン作物であるりんどうの面積が大きくなってしまったた めに、このような余裕もなくなりましたが、一頃はりんどう出荷一色になってしまう前の時期に、ひまわりなどと併せ、束の間の多彩な草花出荷の時期を楽しみました。
小さい花がつぶつぶに寄り集まったアスチルベの花姿。アスチルベは宿根草で、1営農用品種として少量購入した苗を時間をかけて大きい株とし、それを株分けして数を増やしたものを出荷していました。”りんどう農家”にとっては6月 中旬から7月中旬までの1か月は、比較的時間に余裕のある時期。現在ではメイン作物であるりんどうの面積が大きくなってしまったた めに、このような余裕もなくなりましたが、一頃はりんどう出荷一色になってしまう前の時期に、ひまわりなどと併せ、束の間の多彩な草花出荷の時期を楽しみました。

冬の農閑期など、カタログなどを見て何をやるか構想し、栽培の資 料を集めたりすることは楽しいもの。余裕のできる時期に当地域の風土に合った草花や山野草を研究し、導入していく姿勢は常に持っていたいものです。セント ウレア(宿根黄金矢車草)やエリンジウムもきれいに咲いてくれました。ただ雨の多い時期なので、できれば雨よけをしてやりたい感じでしょう か。セントウレアやエリンジウムはドライにすることもできるようで、勉強してみれば面白いと思います。

 ハウスでは、ひまわりを4年続けました。品種は「レモン」や「オ レンジ」「マンゴー」などサンリッチ系の品種です。マルチなしで播種していて雑草は結構になっているけれど、雨の多い7月にハウスの作業を取り入れたこと で気分転換にもなり楽しみな作業でもありました。
ハウスでは、ひまわりを4年続けました。品種は「レモン」や「オ レンジ」「マンゴー」などサンリッチ系の品種です。マルチなしで播種していて雑草は結構になっているけれど、雨の多い7月にハウスの作業を取り入れたこと で気分転換にもなり楽しみな作業でもありました。
2009年からは花の方はりんどうに一本化しております。7月の時期にはりんどうの管 理のほか、小麦とにんにくの収穫がありますので、現在では7月は食べ物の方に切り替えています。これまで手掛けた花々は、種の栽培であるひま わりを除き、少量ずつ標本として空きスペースに移植し、庭木として楽しんでいます。


ひまわりの品種は結構多く、微妙に色合いが異なり楽
しみでした。下は収穫の終わった背 の低い品種(左の方)と、これから切るという背の高い品種です。同じ日に蒔いても開花がずれて作業が楽になりますね。花はりんどうのみに特化し、米野菜との2本立てにしておりますので、このページは過去の思い出となりました。

にんにく
 有機肥料のみで作ったにんにくに は、店で買ったのとは違う味がする。そんなに強烈でないし、たくさん食べても口に後味が残らないような気がする。なぜだろう。肥料のせいか、あるいは時間 をかけた自然乾燥が穏やかな風味をもたらすのか。
有機肥料のみで作ったにんにくに は、店で買ったのとは違う味がする。そんなに強烈でないし、たくさん食べても口に後味が残らないような気がする。なぜだろう。肥料のせいか、あるいは時間 をかけた自然乾燥が穏やかな風味をもたらすのか。
わが家は縁起を担ぐ方ですので、毎年新しく掘ったにんにくを魔よ けとして玄関に吊しています
7月はこのにんにくを始め、小麦、ブルーベリー、りんどうや庭の花など、多彩な収穫が楽しめる時期です。

 近年特ににんにくの需要は高まっているのではないかと思う。健康面もあるが、やはり料理の薬味として幅広く利用できるからだろう。にんにくはすりおろしてカレーにもラーメンに も、焼き魚、豚カツ、豚汁や味噌汁にも結構合うし、最近はハーブと一緒に料理したりすることも多い。にんにくを一日一かけらずつ食べていろんな微量要素を 摂取したいものだ…。
近年特ににんにくの需要は高まっているのではないかと思う。健康面もあるが、やはり料理の薬味として幅広く利用できるからだろう。にんにくはすりおろしてカレーにもラーメンに も、焼き魚、豚カツ、豚汁や味噌汁にも結構合うし、最近はハーブと一緒に料理したりすることも多い。にんにくを一日一かけらずつ食べていろんな微量要素を 摂取したいものだ…。
自分の好物でもあり、また貯蔵もきく、そんな理由で始めたわが家のにんにく。 冷涼を好み乾燥を嫌うにんにくは、カラカラな土にならないここの風土にも合っている。牛糞堆肥とボカシ肥料(+消石灰は必要)のみをふんだんに投入してで きた素朴な味は、スーパーで売っているものとはひと味違うと思う。
にんにく掘り


 にんにく掘りにもコツがあり、がむしゃらに引っ張ると実の部分 を残して茎が切れてしまう。ギックリ腰にもなりかねない。フォークで土をゆるめてから抜いていく。まずマルチを剥がしてから。営農用には青森の代表的な品種(ホワイト福地6片)および青森・ 秋田の評価の高い在来品衆を植えており、9月植え付け、冬越しして翌7月に収穫し、ハウスの中でゆっくり自然乾燥。有機質肥料のみを十分に吸って生育した 無農薬のにんにくは本当にパワーの源だと実感される。種子は3年に一度更新し、大玉をキープできるよう努めています。この種苗代金が高いのが大きく面積を 増やしにくいネックでもあるのですが…。
にんにく掘りにもコツがあり、がむしゃらに引っ張ると実の部分 を残して茎が切れてしまう。ギックリ腰にもなりかねない。フォークで土をゆるめてから抜いていく。まずマルチを剥がしてから。営農用には青森の代表的な品種(ホワイト福地6片)および青森・ 秋田の評価の高い在来品衆を植えており、9月植え付け、冬越しして翌7月に収穫し、ハウスの中でゆっくり自然乾燥。有機質肥料のみを十分に吸って生育した 無農薬のにんにくは本当にパワーの源だと実感される。種子は3年に一度更新し、大玉をキープできるよう努めています。この種苗代金が高いのが大きく面積を 増やしにくいネックでもあるのですが…。
小 麦
 自給自足ということを少しでも考えたならば、必ず小麦を植えることに思いつく。わが農園でも10年前からいろいろ試行錯誤で小麦作りに取り組んできた。多雪地帯という土地柄、春蒔き品種がよいとのアドバイスで特別に春蒔き小麦を入手して栽培したこともあった。しかし何せ春まきだと雑 草と一緒に生育がスタートするわけで、全面蒔きでは完璧に草に負け、条蒔きで何とか少量の収穫に至っていたという状況。そして何年かのブランクの後、正攻法で秋蒔き品種、南部小麦とゆきちからで再挑戦する至った次第です。そしてゆきちからは多雪地に不向きであることがわかり、現在はパンに向くとされる「アリーナ」にバトンタッチしました。
自給自足ということを少しでも考えたならば、必ず小麦を植えることに思いつく。わが農園でも10年前からいろいろ試行錯誤で小麦作りに取り組んできた。多雪地帯という土地柄、春蒔き品種がよいとのアドバイスで特別に春蒔き小麦を入手して栽培したこともあった。しかし何せ春まきだと雑 草と一緒に生育がスタートするわけで、全面蒔きでは完璧に草に負け、条蒔きで何とか少量の収穫に至っていたという状況。そして何年かのブランクの後、正攻法で秋蒔き品種、南部小麦とゆきちからで再挑戦する至った次第です。そしてゆきちからは多雪地に不向きであることがわかり、現在はパンに向くとされる「アリーナ」にバトンタッチしました。
現在は岩手の食文化を築いてきた「南部小麦」とスイス由来の強力粉の「アリーナ」をメインに作付けしています。量は少なく例年100kg前後です。
小麦はあらゆる場面での需要があり、特にパンやクッキー等の菓子 類に生かせるわけで、それはわが家の農業のスタイルの次なるステップに大いに役立ってくれるはずと思っての挑戦である。写真は根雪前の、秋の最終生育段階 の様子ですが、このあと5か月の積雪期に耐えてくれなければならない。秋蒔きの宿命「雪腐れ病」になることなく、写真の勢いのまま春には無事生育を再開復活してほしいもの…。









「可能性」こそが人を動かし、仕事へ駆り立てていく原動力だとするならば、小麦の可能性は 加工まで視野に入れたときに測り知れないものがあるでしょう。将来の営農の姿はどうなっているかわからないが、ベーシックな食べ物から離れた暮らしはしていたくないですね。今年もまた麦の種を蒔きました。
に んじ ん ・ た ま ね ぎ
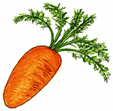 野菜の王様、にんじんは7月に種まきし、10月に収穫。にんじんの 収穫は、ちょうど魚を釣り上げた手応えのように、少し掘って手応えを確かめ、一気に引き抜く面白さがあり、大物をズイっと掘り上げたときは実に気分が良 い。
野菜の王様、にんじんは7月に種まきし、10月に収穫。にんじんの 収穫は、ちょうど魚を釣り上げた手応えのように、少し掘って手応えを確かめ、一気に引き抜く面白さがあり、大物をズイっと掘り上げたときは実に気分が良 い。
うちのにんじんには昔ながらの<にんじん臭さ>があるとよく言わ れる。これも肥料によるのだろうか。わが家では、にんにくはアッサリ系になるが、にんじんは濃厚になるようである。スーパーでふつうに買ういまのにんじん に強い臭いは感じられない。トマトと同様、無臭というかライトな味が好まれる時代なのだと思うが、いかがなものであろうか。
いまはあまりしなくなりましたが、にんじんを使ったケーキ作りにも挑戦し、 しっかりした食感で少量でも満足のいくお菓子に仕上がり、イベントの即売会でも大好評でした。
一方、なかなかうまくいかず苦戦しながら続けているのがたまねぎです。たまねぎの需 要は自家消費の中でもウェイトが高く、にんじんやじゃがいもがあるのだから、これでカレーもできるわけです。当地は酸性土壌のためたまねぎには不適 とされている土地柄の上、有機質しか入れないためあまり大玉にはなりませんが、とれたてのたまねぎの風味は最高です! 採れたては本当に最高の風味なんですが、いか んせん、大きくなりませんで、、、。
ア ス パ ラ ガ ス
 アスパラも順調に生育。春一番に食べられる野菜として重宝です。 有機肥料をたっぷり吸い、健全に生育してくれるよう願います。化成肥料で大きくしたものと違った凝縮された旨味を感じます。
アスパラも順調に生育。春一番に食べられる野菜として重宝です。 有機肥料をたっぷり吸い、健全に生育してくれるよう願います。化成肥料で大きくしたものと違った凝縮された旨味を感じます。
ブ ル ー ベ リ ー 園
 2003 年に植樹した果樹部門。ブルーベリーを3品種、そしてラズベリー(木イチゴ)。近年はやまなし、カシス、サルナシ、それに山ぶどうも加わって、果樹部門は小規模ながら多彩になっています。
2003 年に植樹した果樹部門。ブルーベリーを3品種、そしてラズベリー(木イチゴ)。近年はやまなし、カシス、サルナシ、それに山ぶどうも加わって、果樹部門は小規模ながら多彩になっています。
雪で枝を折られ、なかなか生育が進まない雪国のブルーベリーです が、年月を重ね次第に大きくなり、良い実をたくさん付けてくれるようになりました。生食のほかジャム、ドライにしお菓子の具に。。。農園全体を有 機的にレイアウトし、アグリパークのような性格づけで作付けしていけたらと思い描いており、他の地域の方も招きながら、体験農園も行っていけるような場も提供していきたいと考えています。
気軽に作業に参加していただけるのが、にんにく(7月の収穫や9月の植え付け)と並びこのブルーベリー摘み取りで す。時期は7月中旬~8月上旬です。

 自家菜園は田舎暮らしの魅力の一つ。土壌の関係でこの辺ではできないとされている玉ねぎにも挑戦しています。好物のカレーの具はやは り自給したいですから。
自家菜園は田舎暮らしの魅力の一つ。土壌の関係でこの辺ではできないとされている玉ねぎにも挑戦しています。好物のカレーの具はやは り自給したいですから。
夏は菜っぱ系をたくさん食べ、冬は大根・じゃがいも・にんじん・キャベツ・ね ぎを保存して春までつなぐ。漬け物文化の進んだ地域なので、よく漬け物を戴きますが、大根の一本漬けがその代表格(漬けるときににんにくを入れる手もある)です。
漬け物、ケーキ、お菓子と農繁期以外にもやりたいことは数知れない。都市近 郊部にない沢内・両沢ならではの、この豊かな大自然をバックに楽しい試みを始めてみよう。ここでしか味わえないこと。ここに来てこの空気を吸い、ここで採 れたものを採れたもので味付けし、かまどを使って料理したものを提供する。完全自給は難しくても、それに近づけていこう。そんな構想を、近い将来現実にし よう。まず、そのようなものを作り子どもたちに食べさせて健康に育てることから…。